こうなったら「働き方改革」を先送りにするしかない…「物流の2024年問題」を解決するための奥の手
プレジデントオンライン / 2023年12月20日 7時15分
※本稿は、渡邉哲也『世界と日本経済大予測2024-25』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。
■トラックドライバーがまったく足りない
2023年上半期の企業倒産件数は、帝国データバンクによると4006件だった(負債1000万円以上の法的整理対象)。これは前年同期比31.6%増で、上半期で前年を上回るのは6年ぶりである。
この数値だけを見ると、日本経済の危機とも思えるが、そうした見方は短絡的である。
コロナ禍という空前の厄災に襲われながらも、企業倒産数がそれほど増えなかったのは、ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保)や、補助金・助成金によって助けられてきたから。もともと潰れそうだった企業が、コロナ禍のために生き延びてきたのである。
コロナ禍がいち段落したあとで、そのような企業が結局次々に息絶える状況になったことは、端的に言えば、社会構造の変化に伴う淘汰(とうた)である。
現在見られる新たな傾向は、人手不足による倒産が多いことである。2024年に働き方改革関連法の適用がドライバーの時間外労働時間に及び、上限(年間960時間)が設けられることで、運送業界が大ダメージを負うと言われている。これを「物流の2024年問題」と呼ぶ。
全日本トラック協会では2024年問題によって、輸送能力が14.2%不足し、2030年にはそれが34.1%まで上昇すると試算している(「物流の2024年問題を知っていますか?」『公益社団法人全日本トラック協会』)。
■実体経済にも大きな影響が出るはず
仮に34.1%の輸送能力が不足した場合、今日発送し、明日到着するはずの100個の荷物が、66個しか届かないという事態が想像できる。
同協会では再配達を減らす配慮や、まとめ買いによる運送回数の削減などを呼びかけており、多少の緩和は見られるかもしれないが、抜本的な解決にはほど遠い。
運送業界で貨物・荷物の滞りが発生した場合、実体経済に及ぼす影響は甚大だ。人手不足倒産がさらに拡大する可能性は十分考えられる。
■建設業にも同様の「2024年問題」が
しかしながら、人手不足による倒産であれば、倒産時にそこに勤めている人たちには行き場がある。同じく人手不足の別の職場に転籍が可能だと思われるからだ。
産業構造の変化は、時代の移り変わりとともに、ある程度受け入れざるをえないものだ。政府の使命は、それに伴う失業者を出さないことであって、会社を倒産させないことではない。そこを混同して語る人が多いように感じられる。
直近の2024年問題に関して言えば、特例を設けるなど法的技術で問題を先送りするのが賢明であろう。現状では物理的に人が足りない。

働き方改革関連法の時間外労働の上限規制で、自動車運転業務にかかる部分は2024年4月1日施行と決まっていたが、ここ1、2年、コロナ禍で需要が低迷していたために問題になることが少なかった。
ところが、コロナ禍の一応の収束を見て需要が回復してきたら、「あと1年を切っている」と騒ぎになってきた。日本中で人手不足のなか、より一層人手不足を悪化させて経済が回るはずがない。
建設業界の上限規制も2024年から始まる。このまま何も手を打たなければ、2025年の大阪万博開催も危ぶまれる。
日本国際博覧会協会は、パビリオンの建設に関して、時間外労働の上限規制の対象外にするように政府に求めた。建設が遅れ、輸送が遅れ、オープン前に突貫工事もできないというジレンマに陥っている。
働き方改革と引き換えに国際的信用が失墜する損失をどこまで政府は認識しているのか。そう考えると改正法の施行を遅らせる以外に方法はない。
■日本のキャッシュレス化が進まない理由
2025年の大阪万博では、決済アプリやNFT(Non-Fungible Token=非代替性トークン)が注目され、それを機に一気に一般化すると考えられている。偽造できない電子チケットの役割を果たすNFTが、万博会場外で割引券などの用途にも使えるようになる。万博会場内ではもちろん、全面キャッシュレス決済の方針を明らかにした。

日本では現金決済が今でも根強い現実があり、キャッシュレス化への加速度的な対応が求められている。それを受けて、日本のキャッシュレス比率は2021年で32.5%であるが、2025年6月までに40%という政府目標は何とかクリアできるようである(「キャッシュレスの将来像に関する検討会 とりまとめ」『経済産業省』)。
もっとも世界的に見れば日本のキャッシュレス化は遅れており、韓国93.6%、中国83.0%、豪州67.7%などに大きく遅れをとっている。
これにはさまざまな理由はあるが、一つは日本円の信頼度が高く、偽札がほとんど出回ることはないという事情もありそうだ。
また、キャッシュレス決済のシステム導入にコストがかかるうえ、マージンが3~5%かかるため、零細の自営業者には導入が難しいという点もある。特に飲食業などでは、価格を低く抑えるために現金商売という考えの経営者もいるだろう。
■「NFTチケット」にする意味はあるのか
そのキャッシュレス化も、万博をきっかけに一気に裾野が広がる可能性は否定しない。ただ、NFT自体が価値を持つかというと、一時はそれを商品化しようという動きはあったが、そのベースになる暗号資産が広がらないこともあって頓挫した。
NFTは追跡可能な、偽物を防ぐ手段でしかない。そう考えると、NFTで電子チケットをつくらなくても、電子チケットであれば十分ではないかという気もする。わざわざ高いコストをかけて偽物を防ぐ必要があるのかどうか、考えたほうがいい。
もっとも1970年の大阪万博では、その入場券はたしかにプラチナチケットだったかもしれないが、現代という時代は、万博会場に行かなければ見られないという時代でもない。
どこまでチケットの価値があるのかという点でも疑問が残る。
■開催前に絶対に見るべき70年代の「万博映画」
万博にちなみ、最後に『公式長編記録映画 日本万国博』(1971年 谷口千吉監督)という映画をおすすめしたい。
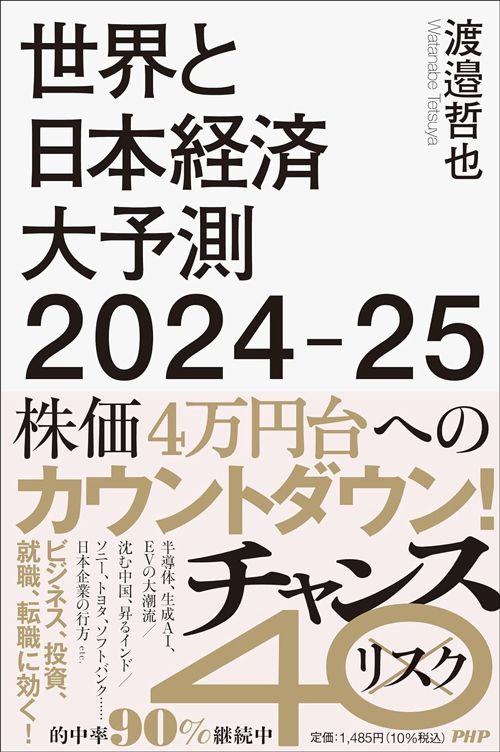
2025年の万国博覧会開催を前に、その55年前に開催された1970年の大阪万博(EXPO'70)が再び注目を集めている。
千里丘陵で開催されたアジア初の万博は、開催半年の間に6000万人以上が集まる歴史的なイベントとなった。本作はその準備から開幕そして閉幕までを追ったドキュメンタリーだ。半世紀以上前の人々の様子や当時の社会風俗を知るにも格好の素材である。
ナレーションは石坂浩二。特撮番組のウルトラQやウルトラマンでのナレーションでも知られ、映像とともに音声でも昭和を感じさせる。
半世紀前の人びとが描いた未来がじつに興味深い。抽象的、流線形、カラフルな建築物が50年前の人が考えた未来だったのかと、今から見ると微笑ましい。その中で、東京ドームそっくりの建築物があるのに驚いたりもする。
■半世紀前の日本の熱気を感じる
各国が1つずつパビリオンを出していたと思っている人が多いかもしれないが、スカンジナビア館はデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国で共同出展されていた。展示品は公害の実態や環境保護を訴えるもので、当時から北欧諸国では環境問題を重視していたことが見て取れる。
当時の日本では四大公害が世間を騒がしており、公害問題はすんなりと受け入れられたと思われるが、環境問題については、まだほとんどの人が意識していなかったのではないか。万博のテーマが「人類の進歩と調和」、時は高度成長の末期とあれば環境保護よりも経済発展に目が行くのは当然で、その意味では北欧らしいと言える。
2時間53分の映像は、今の時代では考えられないような状況も映し出している。閉会式で各パビリオンのコンパニオンたちが、観覧席に座る当時の皇太子夫妻(現上皇・上皇后)に手を伸ばして花を差し出し、それを夫妻が受け取るという距離の近さなどは、警備上の問題からしても、今ではできない相談である。
2025年の万博はおそらくかなり洗練された大人のエキスポとなるだろう。半世紀前の日本が先進国入りした当時の熱気を感じるには、格好の素材、記録映画と言える。万博が開催される前にぜひ見ておきたい記録映画である。
----------
経済評論家
1969年生まれ。日本大学法学部経営法学科卒業。貿易会社に勤務した後、独立。主な著書に、『世界と日本経済大予測』シリーズ(PHP研究所)、『「米中関係」が決める5年後の日本経済』(PHPビジネス新書)のほか、『「中国大崩壊」入門』『2030年「シン・世界」大全』(以上、徳間書店)など多数。
----------
(経済評論家 渡邉 哲也 )
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
アルタガンマ財団とイタリアパビリオンが2025年大阪・関西万博に向けた合意文書に調印
共同通信PRワイヤー / 2024年5月31日 15時14分
-
大阪万博の中止はもう無理なのか…3187億円の税金を使って「カジノ建設の露払い」をするという無責任の体系
プレジデントオンライン / 2024年5月18日 9時15分
-
〈大阪・関西万博 開催の意義を改めて問う〉松本正義・関経連会長を直撃!
財界オンライン / 2024年5月17日 7時0分
-
2025年開催予定の大阪・関西万博は開催すべきか?Surfvoteで集まった意見では開催派と中止派がいずれも33.3%で拮抗。縮小や延期を求める意見も多く寄せられました。
PR TIMES / 2024年5月14日 10時45分
-
Continuum.SocialがAsian Metaverse Summit & Awards 2024にてMost Innovative NFT Projectを受賞
PR TIMES / 2024年5月8日 15時40分
ランキング
-
1日テレがXの投稿削除 雲仙・普賢岳大火砕流巡り
毎日新聞 / 2024年6月5日 22時52分
-
2「ぶっ殺すぞと怒鳴られた」 カスハラ被害46% 小売業の労組調査
毎日新聞 / 2024年6月5日 17時48分
-
3ライブやゲーム大会で一部参加者から「体臭」...関係者から相次ぐ苦言 では一体どうすれば...?
J-CASTニュース / 2024年6月5日 20時10分
-
4生活道路が時速30キロへ、遺族「やっと国が動いてくれた」…法定速度の混在や周知など課題
読売新聞 / 2024年6月5日 20時17分
-
5「最悪パターン」怒りあらわ=再審請求棄却で弁護団―飯塚事件
時事通信 / 2024年6月5日 19時2分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












